本コンテンツはあらすじの泉の基準に基づき制作していますが、本サイト経由で商品購入や会員登録を行った際には送客手数料を受領しています。
映画「この子の七つのお祝いに」基本情報
作品概要
「この子の七つのお祝いに」は、斎藤澪の小説を原作とした1982年公開の日本映画です。監督は増村保造、主演は岩下志麻が務めました。第一回横溝正史ミステリ大賞を受賞した同名小説を、ミステリーとサスペンスの巨匠・増村保造が映画化した意欲作です。
物語は、母の愛に飢えた娘・麻矢の壮絶な復讐劇を軸に展開します。親子の因縁や人間の闇に迫る重厚なドラマと、ラストに待ち受ける驚愕の真相が見どころです。日本が生んだ文芸ミステリーの金字塔を、スリリングに描き切った傑作として高い評価を得ています。
キャスト・スタッフ
- 岩下志麻 : 高橋真弓/麻矢(ゆき子) 役
- 岸田今日子 : 青蛾(高橋麗子) 役
- 根津甚八 : 高橋佳哉 役
- 杉浦直樹 : 母田耕一 役
- 監督 : 増村保造
- 脚本 : 松木ひろし、増村保造
- 原作 : 斎藤澪「この子の七つのお祝いに」
- 音楽 : 大野雄二
- 主題歌 : 小林麻美「めぐり逢い」
受賞歴
- 第6回日本アカデミー賞 最優秀主演女優賞(岩下志麻)
- 第6回日本アカデミー賞 最優秀助演女優賞(岸田今日子)
- 第3回ゴールデングロス賞 助演女優賞(岸田今日子)
- 第24回ブルーリボン賞 主演女優賞(岩下志麻)
- 第24回ブルーリボン賞 助演女優賞(岸田今日子)
「この子の七つのお祝いに」詳細なあらすじ【ネタバレ注意】

物語の発端 – 狂気に囚われた母と娘の奇妙な日常
昭和25年、東京・大森の木造アパートに、真弓と娘の麻矢が住んでいました。2人を捨てて出て行った夫への恨みを麻矢に刷り込む真弓。毎晩「お父さんを恨みなさい、憎みなさい」と言い聞かせる異様な母子関係が10年以上続きます。
麻矢が7歳の正月、晴れ着を着せられ、「あなたのお祝いの日よ」と告げられます。その直後、真弓は娘の目の前で手首を切って自殺。トラウマとなったこの日から、麻矢の復讐の運命が動き始めるのでした。
事件の幕開け – 2つの猟奇殺人が巻き起こす疑心暗鬼
それから30年後の昭和57年、東京の下町で2件の猟奇殺人が発生します。最初の被害者は、派手な男性関係で知られる女性・池畑良子。男による犯行と思われましたが、現場に残されたケーキの空き箱から、サングラスの女が浮上します。
続いて、元新聞記者のフリーライター・母田耕一が無惨な姿で発見されます。別の記者・須藤洋史は、母田が遺した取材ノートから、事件の秘密が会津にあると知ります。会津に向かった須藤でしたが、その最中、池畑の友人・青蛾も惨殺されます。
一連の事件を調査する須藤は、ゆき子というバーのママと知り合います。犯人像が見えない中、須藤はゆき子に惹かれながらも、彼女への疑念を強めていきました。
暴かれる因縁の過去 – 麻矢の復讐劇が始まる
ゆき子の正体こそ、麻矢その人でした。真弓に歪められた愛情を注がれ、復讐心だけを育んで生きてきた麻矢。自分を捨てた実父を探し当て、その罪を償わせるため、周到に計画を練ってきたのです。
母の形見である手形占いを駆使し、政界の黒幕として暗躍する実父・佳哉の情報を得る麻矢。その過程で邪魔となった人物を、一人一人殺害していきました。池畑良子、青蛾、そして真相に迫った母田耕一。麻矢の凶行は、壮絶な親子の物語の幕開けに過ぎなかったのです。
衝撃の真相 – 入れ替わった運命のアイデンティティ
佳哉を人気のないアパートに呼び出した麻矢は、30年前に捨てられた恨みを激白します。しかし、そこで明かされる真実に愕然とします。本当の娘・麻矢は生後まもなくネズミに喰われて死亡。絶望のあまり狂った真弓は、佳哉の後妻との子・きえを盗み、自分の娘として育てていたのでした。
自らのアイデンティティが根底から覆される衝撃。麻矢=ゆき子の復讐劇は、思わぬ方向へと暴走します。麻矢を溺愛しながらも疎んでいた真弓。その真意を知り、失意の淵に立たされる麻矢。狂気の親子の物語は、悲劇的な結末を迎えるのでした。
「この子の七つのお祝いに」のラストシーンとエンディングの意味
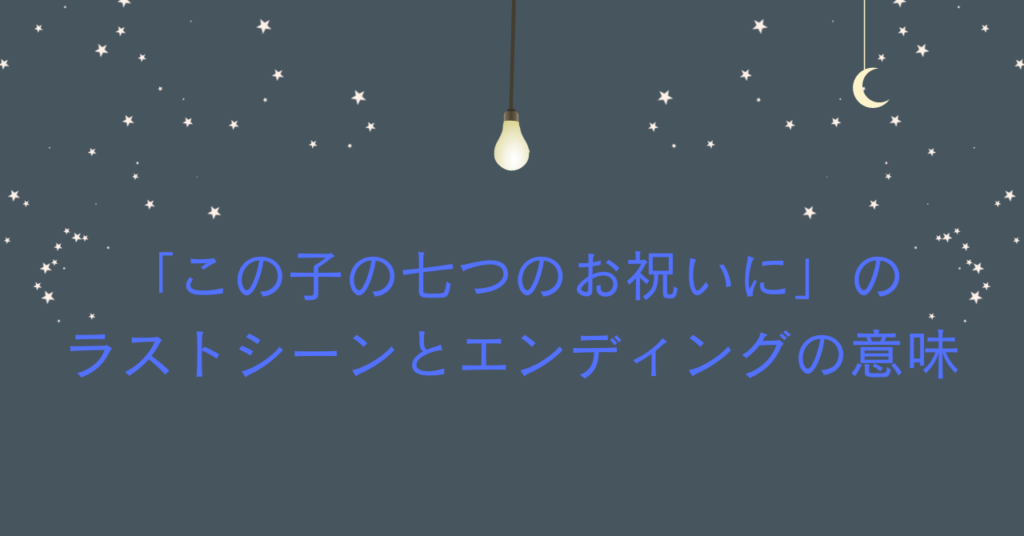
悲劇的結末 – 崩壊する麻矢の精神と復讐の果て
真実を知り、自我崩壊する麻矢。自分が麻矢ではないと知った時、彼女の心は完全に砕け散ってしまいます。「通りゃんせ」を口ずさみ、現実と狂気の狭間をさまよう姿は悲痛です。
「あたしはいったい何なの?」。自分のアイデンティティを完全に見失った麻矢。母の愛に飢えながら、その愛ゆえに狂わされた半生。佳哉への復讐も、真弓への復讐も、全てが水泡に帰した瞬間でした。
ラストシーンで、自我を失った麻矢はふたたび「通りゃんせ」を歌います。そのことばには、「この世とあの世をいったりきたり」という意味が込められています。現世に未練を残しながら、理不尽な運命に翻弄された哀れな麻矢。彼女にとって、死と隣り合わせの、救いようのない日々だったのかもしれません。
エンディングの余韻と解釈
麻矢の結末を見届けたとき、観る者の心には言い尽くせない虚しさが残ります。彼女は本当に救われたのでしょうか。狂気に満ちた愛情を注いだ真弓、娘を捨てながらも憎みきれなかった佳哉。そして、自分のアイデンティティさえも失った麻矢。彼らに本当の救済はなかったのかもしれません。
ただ一つ確かなのは、愛憎に彩られたこの親子ドラマが、同時に人間の孤独と絶望を浮き彫りにしたことです。「この子の七つのお祝いに」が問いかけるのは、家族の絆とは何か、人を愛するとは何かということ。悲劇のラストに込められた難解なテーマを、私たちは反芻せずにはいられません。
「この子の七つのお祝いに」の見どころ・トリビア
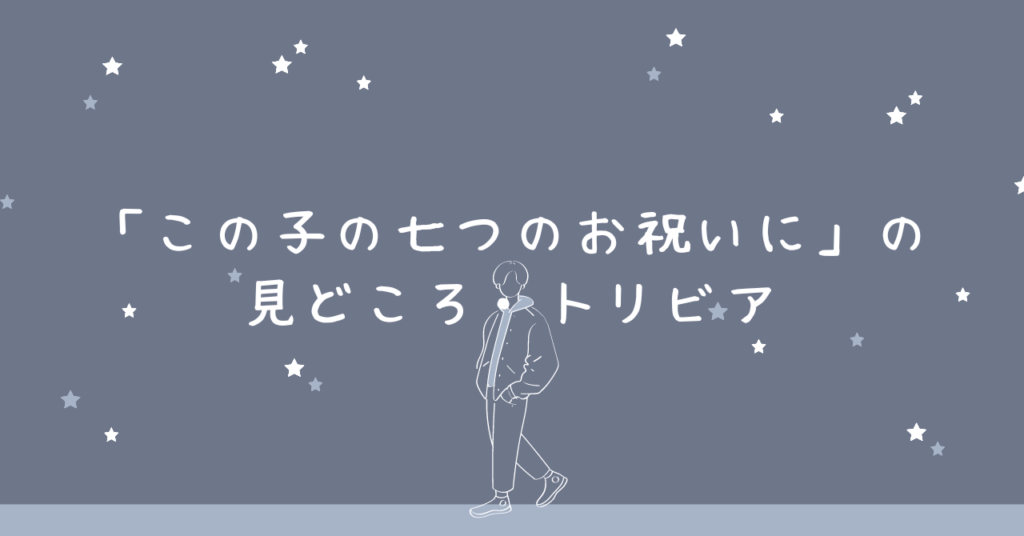
シンボリックな表現と演出
本作では「手形」と「ケーキ」が重要なモチーフとなっています。
真弓が残した「手形」は、麻矢にとって母の愛情の証であり、同時に復讐心を刻み付けたものでもあります。「青蛾」の手形占いは、麻矢の計画を手助けすると同時に、彼女を狂気へと導きます。「手形」は、愛憎に彩られた母娘の絆の象徴と言えるでしょう。
「ケーキ」もまた、物語全体を貫く鍵となるアイテムです。事件のきっかけとなる池畑良子の死体のそばには、ケーキの空き箱が残されていました。真弓が自殺した麻矢の7歳の誕生日。そこにもケーキがありました。「ケーキ」は、歪んだ親子関係と、悲劇的な運命の暗示として機能しているのです。
ミステリアスな伏線と悲劇へのフォーシャドーイング
映画冒頭の麻矢の7歳の誕生日。真弓は「あなたのお祝いの日よ」と告げて自殺します。普通なら祝福される日のはずが、皮肉にも母を失う悲劇の日となった麻矢。真弓のことばは、娘の人生最大の不幸を予言していたのです。
池畑良子を殺害する際、犯人が購入したケーキ。そのケーキは「モンブラン」でした。これは、真弓が最期に食べたケーキと同じ種類だったのです。偶然の一致ではなく、明らかに事件とつながりのある伏線となっています。
母田や須藤が調査する「会津」の謎。佳哉と真弓の因縁、そして麻矢の誕生の秘密は、すべて「会津」に隠されていました。「会津」は、真相解明の鍵であると同時に、登場人物の悲劇的な運命が交差する場所でもあったのです。
出生の秘密がもたらす驚愕のどんでん返し
ラストで明かされる衝撃の事実。麻矢の正体が、実は佳哉の後妻の子・きえだったというどんでん返しは、観る者を驚愕させずにはおきません。
自分が麻矢ではないと知った時の、ゆき子の絶望と動揺。「あたしは何なの?」と崩れ落ちるゆき子を見て、思わず息を呑みます。自らのアイデンティティが完全に覆される衝撃。そのどん底の心境を、岩下志麻の演技が見事に表現しています。
狂気に憑りつかれるまで麻矢を愛した真弓。その異常な愛情は、実の娘を失ったゆえの歪みだったのです。佳哉を恨みながら、きえを盗み、自分の娘として育てる。真弓の狂気は、愛する者を失ったことで増幅されていったのでしょう。
映画「この子の七つのお祝いに」の評価と考察
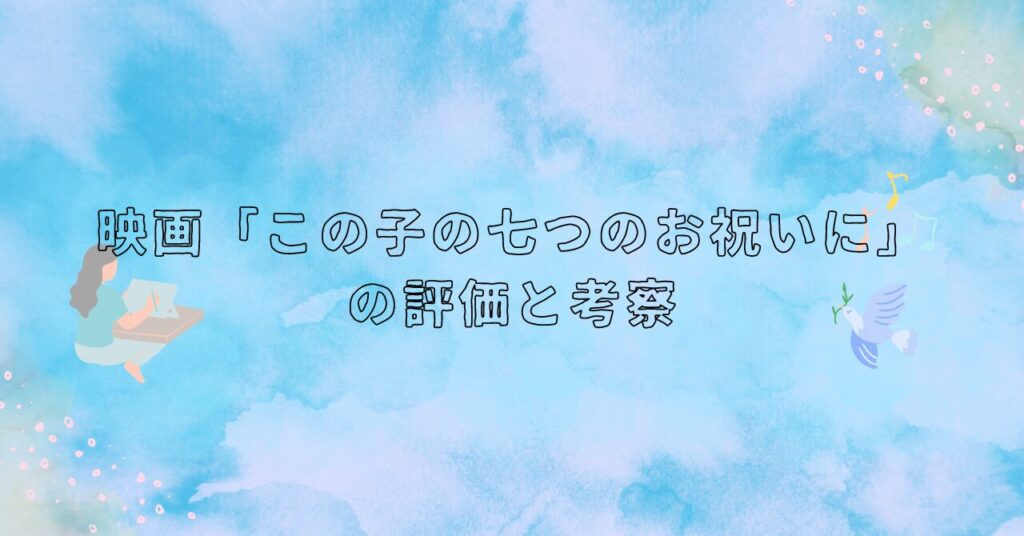
「この子の七つのお祝いに」は、単なる復讐劇というよりは、愛憎渦巻く親子三代の悲劇を描いた重厚な人間ドラマと言えます。
狂気じみた母の愛情に翻弄され、自我を失っていく娘の姿は痛ましくもあり、同情せずにはいられません。真弓にとっても、愛する娘を失った悲しみは、計り知れないものだったのでしょう。歪んだ愛情表現は、母性の闇の部分を象徴しているようにも思えます。
佳哉もまた、娘を捨てたことを後悔しながら、息子の晋太郎を溺愛するなど、父親としての贖罪に苦しんでいたのかもしれません。麻矢に対する複雑な感情は、彼なりの愛情の裏返しだったのでは、と考えさせられます。
人間の心の奥底にある愛憎や悲哀を、巧みな心理描写とミステリー性で表現した秀作です。なぜ人は愛する者を傷つけてしまうのか。家族の絆とは何か。この映画が投げかける問いは、観る者の心に深い余韻を残すことでしょう。
母と娘、父と娘、そして自分自身との対峙を通して、家族の絆や自我の本質を問う哲学的テーマ性も感じられます。誰もが多かれ少なかれ抱える、アイデンティティの揺らぎや存在意義への問いは、現代を生きる我々にも通じる普遍的命題だと言えます。
また、70年代から80年代にかけての東京の下町を舞台に、リアリティある人間ドラマが展開されているのも魅力の一つです。当時の世相や社会情勢を背景に、登場人物たちの苦悩や葛藤が克明に描かれています。時代と人間心理の交錯を鮮やかに切り取った、雰囲気のある映像美も印象的です。
キャスティングの妙も光っています。岩下志麻による麻矢の狂気じみた演技は、彼女の代表作の一つと評されるほどの迫真の迫力です。母親役の岸田今日子も、愛憎に引き裂かれる複雑な心情を熱演。ベテラン俳優陣が織りなす重厚な芝居は、映画のクオリティを大きく引き上げています。
弱冠26歳にして、増村保造監督がこれだけ心理の機微に満ちた難解な原作を完璧に映画化したことにも脱帽です。ミステリーの巨匠・横溝正史に認められた、斎藤澪の原作の凄みを余すことなくスクリーンで表現しきったと言えるでしょう。
まとめ:「この子の七つのお祝いに」から受け取るメッセージ

「この子の七つのお祝いに」は、ミステリーとサスペンスを基調としつつ、親子関係の本質を問う、スリリングな家族ドラマです。真弓・麻矢・佳哉という三者三様の愛憎が交錯する様は、観る者の心を揺さぶってやみません。
歪んだ愛情表現ゆえに、母に心を壊され、自我を失った娘。自らのルーツが覆された時、麻矢=ゆき子が味わった絶望は、人間の心の脆さを物語っています。自分は何者なのか。存在意義とは。麻矢の悲劇は、現代人の抱える普遍的な問いかけでもあるのです。
また、真弓や佳哉の苦悩からは、親としての贖罪や、家族への背徳がもたらす代償の大きさを感じずにはいられません。麻矢への異常な愛情も、きえを奪ったことの罪悪感も、根底には「親」であるがゆえの感情があったのかもしれません。
誰しもが多かれ少なかれ抱える、家族との軋轢。相手を思うあまり、時に歪んだ形で爆発してしまう感情。この映画が提示する、血の絆をめぐる命題は、人間ドラマの核心を突いていると言えるでしょう。
狂気じみた復讐劇の果てに、麻矢が最後に辿り着いた境地とは何だったのか。救いのない悲劇のようにも思えますが、人生に迷った彼女が出した答えなのかもしれません。真弓への、そして自分自身への許しと、新たなる旅立ち。「通りゃんせ」の歌は、そんなメッセージ性を感じさせずにはおきません。
「この子の七つのお祝いに」が問いかけるテーマは、今なお色褪せない普遍性を持っています。この悲劇的物語が、現代を生きる私たち一人一人に、家族の絆とは何か、愛するとは何かを問いかけているのです。



