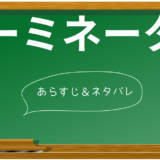本コンテンツはあらすじの泉の基準に基づき制作していますが、本サイト経由で商品購入や会員登録を行った際には送客手数料を受領しています。
『ジョーカー』とは?作品の基本情報を紹介
『ジョーカー』は、DCコミックスの人気キャラクター”ジョーカー”を主人公にしたアメリカの映画作品です。バットマンの宿敵として知られるダークヒーローの誕生を描いた、スタンドアローン作品として2019年に公開されました。
監督は『ハングオーバー!』シリーズなどのトッド・フィリップス、主演はホアキン・フェニックスが務めています。アメリコミ原作映画としては異例の、第76回ヴェネツィア国際映画祭での金獅子賞受賞をはじめ、アカデミー賞でも作品賞を含む11部門でノミネートを果たした話題作です。
その一方で、社会的弱者の孤独と怒りを赤裸々に描いた内容が賛否両論を巻き起こし、全米各地で公開中止になるなど物議を醸した作品でもあります。そのリアルな問題提起が大きな議論のきっかけとなりました。
主人公アーサー・フレックについて

ゴッサム・シティで暮らす孤独なピエロ
『ジョーカー』の主人公アーサー・フレックは、ゴッサム・シティのスラム街に住む孤独な男性です。生まれつき体に障害を抱え、人前で突然笑い出してしまうという特異体質。母親ペニーと2人で暮らしながら、ピエロの仕事で糊口をしのいでいます。
母親との確執、周囲からの虐げが深い傷に
アーサーは幼い頃、母親の恋人から虐待を受けた経験を持ちます。その結果残った心の傷が、先述の突然笑い出す障害にもつながっているようです。
母親ペニーもまた、アーサーに愛情を注ぐ一方で過干渉気味。彼女との関係性もアーサーにとっては重荷となっています。
加えて、日々の生活の中でも周囲の人々から虐げられ続けるアーサー。彼の内面には、癒えない傷がいくつも刻まれているのです。
次第に歪んでいく精神と、暴力への傾倒
自身の存在意義を見出せないまま、日々絶望感を募らせていくアーサー。彼の精神は次第に不安定さを増していきます。
社会への怒りと憎悪、そして母への反発心。混沌とした感情が彼の中でうずまき、やがて暴力への傾倒を生むことになります。
銃社会アメリカの犠牲者であり、そして加害者ともなったアーサー。彼の復讐心が、のちの”ジョーカー”を生み出すきっかけとなるのです。
あらすじ①:アーサーの日常と挫折

ピエロの仕事で糊口をしのぐアーサー
アーサーは、子供向けのピエロとして働き、細々と生活を送っています。ある日の仕事中、若者グループに絡まれ、ひどい暴行を受けてしまいます。同情した同僚から、護身用の拳銃を渡されるシーンがあります。
地下鉄で3人の証券マンを射殺
地下鉄の車内で、酔っ払った証券マンたちに絡まれたアーサーは、怒りから拳銃を取り出します。撃った弾は3人の命を奪い、アーサーは慌てて逃走。この衝動的な殺人により、彼の中に暴力への衝動が芽生え始めるのです。
世間はこのニュースに色めき立ち、ピエロのマスクが一種の抗議のシンボルとなっていきます。アーサーの孤独な闘いは、いつしか社会現象へと発展していくことになるのです。
あらすじ②:殺人と覚醒

精神の均衡を失い、母親を殺害
アーサーは母親ペニーから、昔ウェイン家に務めていたことを聞かされます。ペニーはウェインに手紙を書くようアーサーに頼みます。
しかしその後、ペニーの入院先でショッキングな事実が発覚します。ペニーが幼いアーサーを虐待していたのです。この事実に激高したアーサーは、枕で母親を窒息死させてしまいます。ペニーの死は、アーサーの精神の均衡を決定的に崩すことになります。
人気トークショーに出演、復讐を宣言
そんな中、人気トークショーで司会者がアーサーを招きます。アーサーはテレビで自分のことを「ジョーカー」として紹介するように頼みます。
すっかり正気を失ったアーサーは、番組の生放送で司会者を撃ち殺してしまいます。一気にゴッサム・シティは混乱に陥ります。アーサーを熱狂的に支持する、ピエロに扮した群衆が街を埋め尽くすのです。
衝撃のラストシーン
場面は一転し、アーサーは手錠をつけて精神鑑定を受けています。カウンセラーとの会話を適当に終わらせた彼は、血の足跡を残しながら歩き、窓際で踊りだします。病院の職員に見つかった彼は、そこら中を逃げ回るのでした。
『ジョーカー』見どころ①:ホアキン・フェニックスの名演技
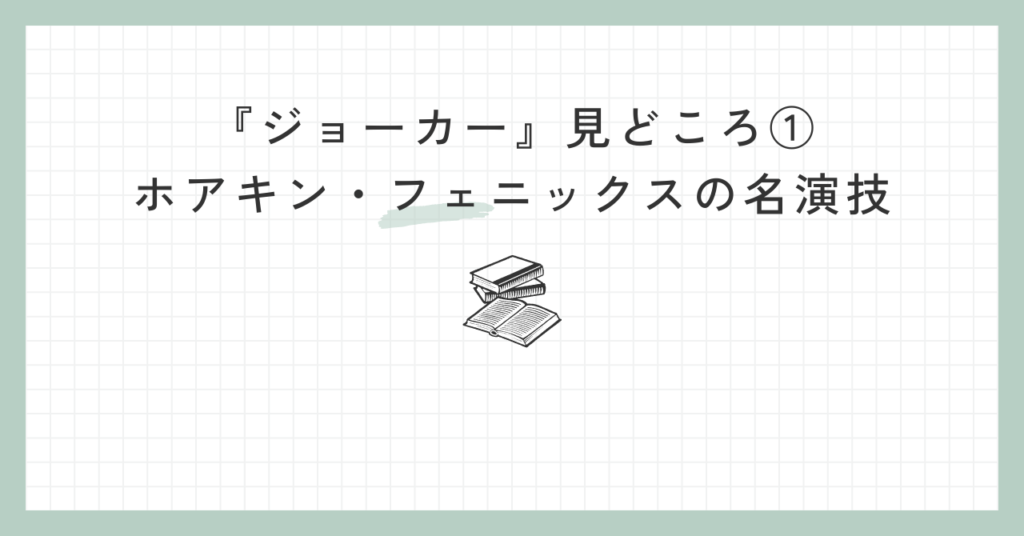
ピエロからジョーカーへと変貌を遂げる様を熱演
本作の最大の見どころは、何と言っても主演のホアキン・フェニックスの圧巻の演技でしょう。アーサーからジョーカーへと変貌を遂げる様を、全身全霊で演じ切っています。
その演技力が認められ、アカデミー賞主演男優賞を見事に射止めました。
特に印象的なのが、ジョーカーへの覚醒を象徴するダンスのシーン。カラフルな衣装に身を包み、ゴッサムの街を踊り歩くアーサー。その妖しくも美しい姿は、まさに怪演と呼ぶにふさわしい仕上がりです。
不安定な精神を体現する身体表現と絶叫
アーサー特有の奇声と身体の痙攣を、ホアキンは見事に体現しています。感情の起伏が激しく、常に不安定な精神状態にあるアーサー。その内面をあぶり出すかのような、ホアキンの身体表現からは目が離せません。
また、クライマックスで絶望の絶叫を上げるシーンは圧巻。ホアキンの演技力なくしては成立し得ない、劇中屈指の名シーンと言えるでしょう。
孤独に耐えかね、妄想の中に逃避するアーサーを、ホアキンは実に繊細に演じ上げています。無垢な子供のような純真さと、歪んだ狂気とを併せ持つアーサー像は、ホアキンの演技あってこそ。彼の名演技は本作の大きな見どころの一つです。
『ジョーカー』見どころ②:こだわりの映像美と音楽
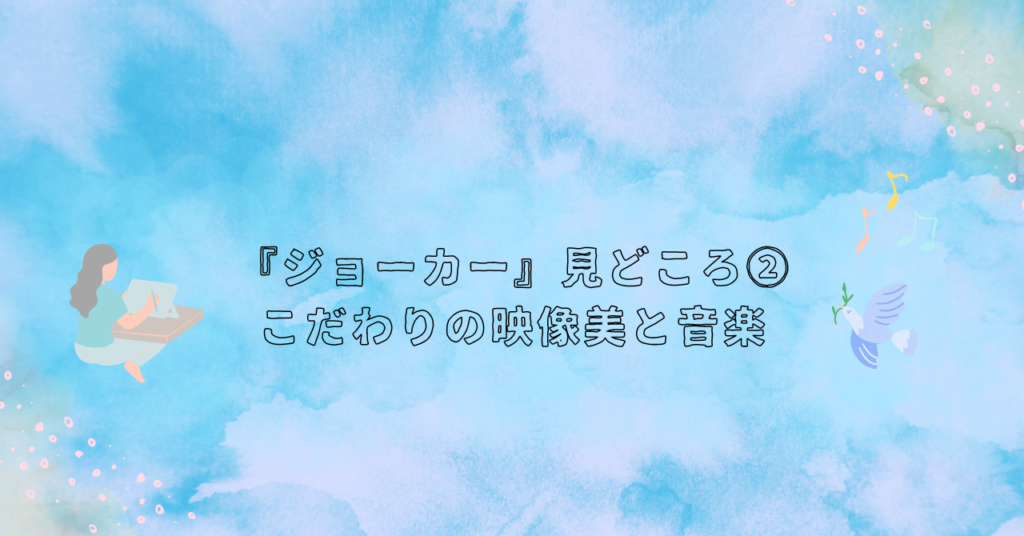
70年代の雰囲気を見事に再現した美術
本作のもう一つの見どころは、徹底的にこだわり抜かれた映像美です。撮影監督のローレンス・シャーは、1970年代の雰囲気を絶妙に再現しています。
セピア調の色調が、作品全体に重厚感を与えています。まるで当時の写真を眺めているかのような、ノスタルジックな空気感が漂います。
ゴッサムの街並みや、アーサーの自宅といったセットもまた秀逸。所々に散りばめられた小道具が、生活感とリアリティを感じさせてくれます。スラム街の窓から見える、汚れた煉瓦の壁。アーサーの部屋に置かれた、安っぽい家具の数々。どこか懐かしくも、不穏な空気を感じさせる美術は、アーサーの心象風景を代弁しているかのようです。
不穏な空気を醸成するBGMの効果的な使用
映画の劇伴を手がけたのは、作曲家のヒルドゥル・グーナドッティル。ハープの旋律を軸に、終始不穏な空気を醸成するBGMは、観る者の心を圧迫します。
特に、アーサーが自分を見出し、ジョーカーへと「覚醒」する「ステップ・ダンス」のシーンで流れるロック音楽の使い方は絶妙です。まるでアーサーの感情に寄り添い、観客を彼の心情に引き込むかのようなBGMの使い方。音楽一つをとっても、監督のこだわりが感じられます。
フィナーレの、七面鳥の丸焼きをナイフで切り分けるシーンで響く皿の音。それはこの後に起こる惨劇を暗示しているかのよう。このように、BGMが物語の伏線となっているのも、本作の見どころだと言えるでしょう。
社会派メッセージ:格差と分断への怒り

富裕層と下層民の対立構図が生む悲劇
『ジョーカー』は、単なるヒーロー映画の枠を超えた、社会派メッセージ性の強い作品だと言えます。作中では富裕層と下層民の対立構図が色濃く描かれており、ウェイン家に象徴される上流階級への反発が、物語を貫いています。
精神疾患を抱える人々への偏見や、貧困に苦しむ人々の苦境が赤裸々に描写されるなど、現代社会の分断を告発するような内容となっています。格差によって生まれる、負の連鎖。本作はそれを、痛いほどリアルに映し出しているのです。
共感と扇動のはざまで読み解く”ジョーカー像”
しかし一方で、社会不適合者による犯罪行為を美化しているのではないか、という批判の声もあがりました。公開当時、社会現象とも言えるカルト的人気を背景に、倫理的な議論が巻き起こったのです。
興味深いのは、本作があえてアーサーを、単なる被害者とも加害者とも描いていない点。彼の行動の是非を観る者に問うことで、私たち一人一人の価値観を問い直しているようにも感じられます。
アーサーに共感するか、それとも彼を非難するか。この問いに対する答えによって、作品から読み取れるメッセージは大きく変わってくるでしょう。善悪の境界線があいまいなアーサー像は、現代社会の抱える問題を浮き彫りにしていると言えるかもしれません。
まとめ:新しいジョーカー像を確立した衝撃作

以上見てきたように、『ジョーカー』はヒーローとヴィランの境界線を曖昧にした、問題提起型の衝撃作だと言えるでしょう。アーサーという男の生い立ちを丁寧に描くことで、これまでにない”ジョーカー像”を見事に確立しているのです。
一人の男が、どのように狂気に至るのか。その過程を赤裸々に描き出すことで、観る者の倫理観を大きく揺さぶります。そこには、現代社会の闇を凝視するような強烈なメッセージ性が息づいているのです。
社会の分断と格差に対する怒りの矛先は、時に凶行へと向かう。『ジョーカー』は、そんな負の連鎖を生々しく映し出した作品と言えるでしょう。アーサーに共感するか非難するかは、観る者次第。結論を提示することなく、あえて観客に問いを投げかける姿勢が、この映画の真骨頂だと言えます。
それを、エンターテインメント作品として昇華させたのが本作の偉業。圧倒的な映像美とホアキン・フェニックスの怪演は、必見の価値ありです。
社会に新たな問いを提起した衝撃作。「ジョーカー」という存在を通して、私たち一人一人の在り方を問う。色褪せることのない強いメッセージを放つ『ジョーカー』は、間違いなく映画史に残る1作となることでしょう。