本コンテンツはあらすじの泉の基準に基づき制作していますが、本サイト経由で商品購入や会員登録を行った際には送客手数料を受領しています。
芥川龍之介「鼻」の基本情報
執筆時期と初出
芥川龍之介の短編小説「鼻」は、1916年に執筆され、同年9月号の文芸雑誌「新思潮」に初めて掲載されました。大正時代初期の作品であり、芥川が本格的に文壇で活躍し始めた頃の代表作の一つと言えます。
あらすじを知る前に – 作品の特徴
「鼻」は、主人公である禅智内供という僧侶が自分の長い鼻を気にして悩む姿を描いた物語です。芥川自身も自意識過剰な性格であったと言われており、その性質が作中人物に投影されていると考えられています。短編小説でありながら、主人公の心理描写に重点が置かれているのが特徴です。
「鼻」のあらすじを簡潔に紹介

主人公・禅智内供の悩み
物語の主人公である禅智内供は、自分の鼻の長さを気にしています。鼻が異様に長いことを恥ずかしく思い、人前に出ることを避けるようになりました。
鼻を短くする方法
ある秋の日、京都から戻った弟子が、医者に鼻を短くする方法を教えてもらったと言いました。興味を持った内供は、その方法を試してみることにしました。その方法とは、熱湯で鼻を茹でて、その後に弟子がその鼻を踏み、出てきた脂を毛抜きで取り除き、もう一度鼻を熱湯で茹でるというものでした。実行すると、もともと顎下まであった異常に長い鼻が見事に縮んで、普通の人と同じサイズになりました。これにより、他人からの嘲笑を恐れることがなくなったと内供はほっと一息つきました。しかし、2、3日が経過した後、彼は思いがけない事実に気付くのでした。
人々の嘲笑
鼻を短くした内供を見た人々が、なんと以前よりもさらに大声で笑い始めたのです。当初、内供は自分の顔が急激に変わったために人々が驚いているのだと考えました。しかし、その説明だけでは人々の嘲笑が過剰である理由を完全には解明できず、その状況に不気味さを感じ始めました。結局、彼は再び落ち込み、最終的には以前の長い鼻が恋しくなるほどにまで心が揺れ動くのでした。
元に戻った鼻
人間の心には矛盾する二つの感情が共存しています。一方では他人の不幸に対して同情する心を持ちながら、その人が何とかして困難を乗り越えたときには、どこか満足できず、再び不幸に陥れたいという敵意のようなものを抱くのです。内供もその例に漏れず、彼が鼻を短くした後、周囲の反応は思わぬものでした。その後、内供は熱を出して寝込むことになり、その間に彼の鼻は元の長さに戻りました。鼻が元通りになったことで、もはや誰からも笑われることはなくなり、彼はすっきりとした気持ちになったのです。
「鼻」のテーマと象徴性を解説
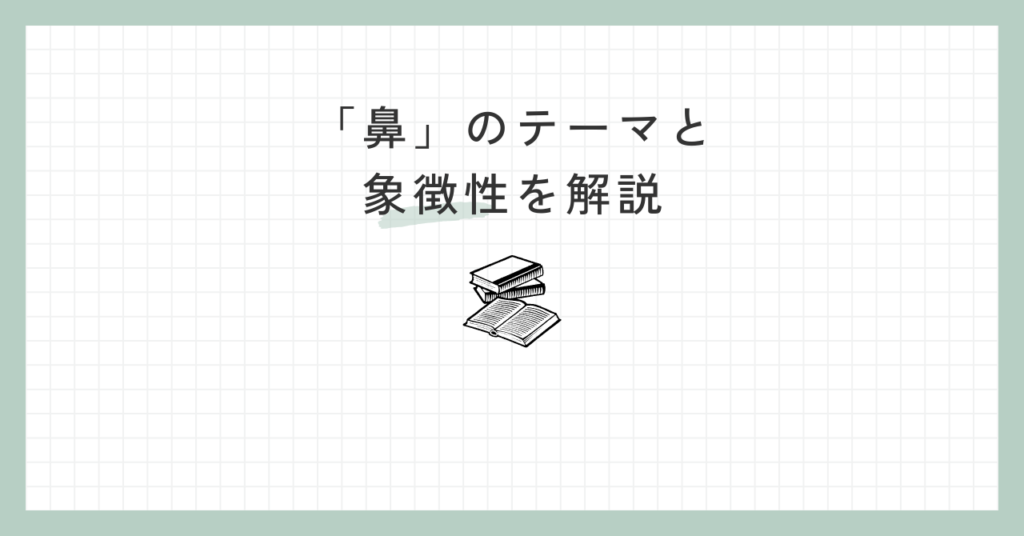
自意識過剰がもたらす悲劇
「鼻」の中心テーマは、自意識過剰が招く悲劇です。主人公の禅智内供は、自分の鼻の長さばかりを気にするあまり、周囲との関わりを避けるようになります。しかし皮肉にも、そうした彼の行動が人々の嘲笑を招く結果となってしまうのです。
鼻が象徴するもの
作中で禅智内供の鼻は、彼の自意識の象徴として機能しています。鼻を気にし過ぎる描写は、自己の特異性に過剰にとらわれる禅智内供の内面を表現しているのです。
芸術家の孤独
また、「鼻」には芸術家の孤独というテーマも読み取れます。周囲の理解を得られない禅智内供の姿は、芸術家が社会から疎外される様子と重なります。芥川自身も、孤高の作家として知られていました。
芥川文学における「鼻」の位置づけ
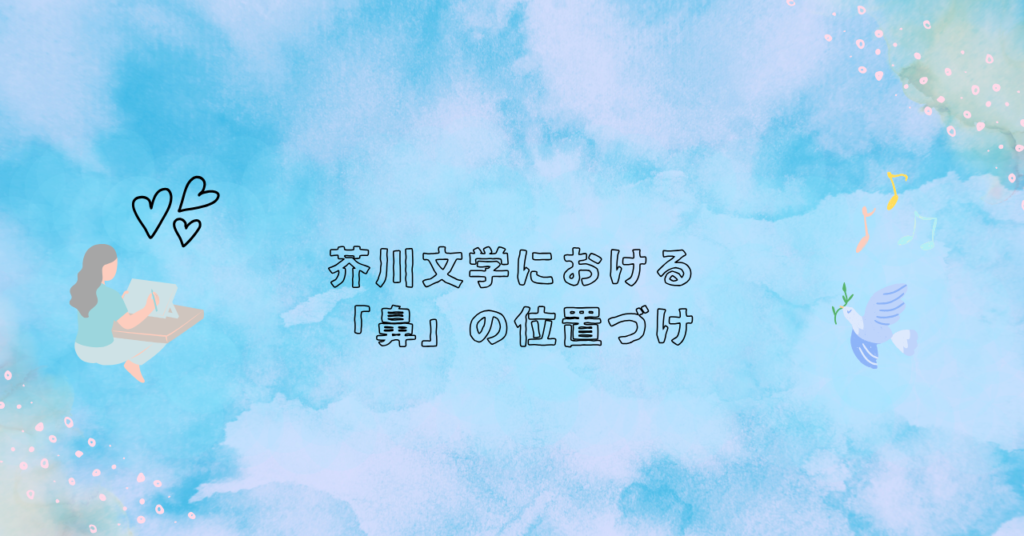
私小説的要素の顕在化
「鼻」は、芥川文学の初期を代表する作品の一つです。この作品では、芥川自身の性格が色濃く反映された私小説的要素が顕著に見られます。主人公の禅智内供の自意識過剰な性格は、芥川自身のそれと重なる部分が大きいと言えるでしょう。
芥川独特の心理描写
また、「鼻」には芥川文学の特徴である心理描写が巧みに用いられています。登場人物の内面を深く掘り下げ、その心理状態を克明に描写する手法は、芥川の他の代表作にも共通して見られるものです。「鼻」は、そうした芥川文学の特徴を初期の段階から示している意欲作と言えます。
まとめ:現代に通じる「鼻」の魅力

芥川龍之介の「鼻」は、1916年に発表された作品でありながら、現代にも通じる魅力を持っています。自分の鼻を気にして自意識過剰になるあまり周囲との関係がうまくいかなくなる禅智内供の姿は、現代人の抱える悩みを先取りしているようにも見えます。
また、「鼻」には芥川文学の真髄とも言える巧みな心理描写が凝縮されています。登場人物の内面を深く掘り下げるその手法は、現代の読者にも強い訴求力を持つことでしょう。
わずか数ページの短い物語でありながら、「鼻」は読む者の心に深く残る作品です。芥川文学の入門編として、また現代に通じる普遍的テーマを持つ物語として、「鼻」はこれからも多くの読者を獲得し続けるに違いありません。



