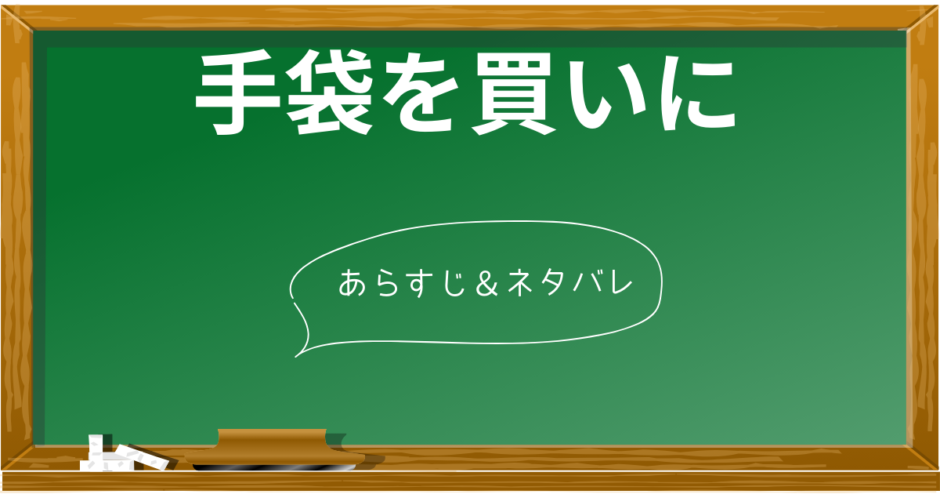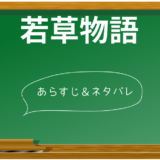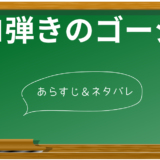本コンテンツはあらすじの泉の基準に基づき制作していますが、本サイト経由で商品購入や会員登録を行った際には送客手数料を受領しています。
新美南吉の「手袋を買いに」は、日本の児童文学の金字塔とも言える名作です。ある冬の日、子狐が手袋を買いに出かける物語は、一見するとありふれた童話の風景を切り取ったものに過ぎません。しかし、その温かな筆致で綴られた言葉の一つ一つには、自立と成長、絆と愛情、勤勉と誠実といった、普遍的な人間の美質への讃歌が込められているのです。
本記事では、「手袋を買いに」のあらすじを丁寧に追いながら、「手袋を買いに」が放つメッセージを読み解いていきます。作家・新美南吉の生涯と時代背景にも触れつつ、この小さな物語が現代を生きる私たちに投げかける、大きな問いについて考察してみましょう。
小説「手袋を買いに」とは? 作品の背景

新美南吉の生涯と作風
新美南吉は、1913年に愛知県に生まれた。幼くして両親を亡くし、親戚の家を転々とする不遇な境遇の中で育ちました。そうした中でも、南吉は文学への情熱を育み、旧制中学卒業後は小学校代用教員を務めながら、童話や詩の創作に励みました。
南吉の作品には、社会的弱者への深い共感と、庶民の日常への温かいまなざしが貫かれています。代表作「ごん狐」「手袋を買いに」「牛をつないだ椿の木」などには、人間の尊厳を見つめる作家の眼差しが宿っています。私小説的な筆致で綴られる作品群は、日本児童文学の金字塔として高く評価されています。
物語の舞台と時代背景
「手袋を買いに」が発表されたのは、1938年。昭和初期の日本は、第一次世界大戦後の大正デモクラシーの影響を受けつつ、関東大震災後の復興期にあった。モダニズム文学が隆盛し、社会の価値観が大きく揺れ動いていた時代である。
新美南吉の生涯と時代背景を踏まえることで、「手袋を買いに」の持つリアリティとメッセージ性がより立体的に浮かび上がってくる。次章からは、物語のあらすじを丁寧に追っていこう。
「手袋を買いに」のあらすじ:子狐のおつかい

雪の朝と子狐の冷たい手
ある雪の日の朝、遊び疲れて帰宅した子狐が「手が冷たい」と母さん狐に訴えました。子狐の手は冷たい雪で牡丹色に変わっていたため、母さん狐は子狐に手袋を買うことを決心します。彼女は冷えた手を温めながら、その決意を固めました。
母狐の過去と町への訪問
夜、狐の親子は人間の住む町へ向かいました。しかし、町の明かりを見ると、母さん狐は過去に人間によって酷い目に遭わされた記憶が蘇り、足がすくんでしまいます。その恐怖を乗り越えることができず、子狐に一人で手袋を買いに行かせる決断をします。
子狐の勇気と帽子屋での一幕
母さん狐は子狐の片手を人間の手に見せかけ、その手だけを帽子屋の戸口に差し入れて手袋を購入するよう指示しました。町に着いた子狐は帽子屋の戸を叩き、計画通りに行動しようとしますが、突然の眩しい光に驚いて本来の狐の手を差し入れてしまいます。帽子屋は狐が化かしに来たと疑いますが、子狐が持っていたお金が本物であることに気づき、黙って手袋を渡します。
手袋の購入と母狐の思索
子狐は無事に手袋を買い、帰宅してからの出来事を母さん狐に報告します。「人間って少しも怖くない」と子狐が話すと、母さん狐は「人間は本当はいいものなのかしら」と自問自答しながら、少し安心した様子であきれるのでした。
まとめ:「手袋を買いに」から得られる教訓

- 過去の経験に囚われないこと – 母さん狐は過去の悪い記憶によって行動が制限され、恐怖を感じてしまいますが、子狐の行動から新しい視点を得ることができます。過去の経験に基づいて未来を決めつけず、新たな可能性に目を向けることが大切です。
- 若い世代に学ぶ勇気 – 子狐は未知の状況にも関わらず、必要な行動を取り、成功を収めます。若い世代が新しい環境や挑戦に果敢に挑む様子から学ぶことは多いです。異なる世代から学ぶことで、新たな解決策や理解が得られるかもしれません。
- 誤解を解く誠実さ – 子狐が誤って自身の本来の手を見せたにも関わらず、帽子屋は子狐が持っていたお金が本物であることを理解し、適切な対応をします。誤解や先入観に基づいて即断せず、事実を確認することの重要性が示されています。
- 恐怖を乗り越える小さな一歩 – 母さん狐が最終的に子狐の経験を通じて人間に対する見方が少し変わることから、恐怖や不安を乗り越えるためには、小さな一歩を踏み出す勇気が必要であると教えられます。
これらの教訓は、日々の生活や人間関係においても応用可能です。過去の困難に対する理解を深めつつ、新しい経験や挑戦に開かれた姿勢を持つことが、成長と発展につながることを示唆しています。