本コンテンツはあらすじの泉の基準に基づき制作していますが、本サイト経由で商品購入や会員登録を行った際には送客手数料を受領しています。
山川方夫「夏の葬列」とは?作品の背景を解説
山川方夫の経歴と代表作
山川方夫は1922年東京生まれの小説家です。太平洋戦争後の1946年に小説家としてデビューし、戦争体験を元にしたリアリズム作品を多く発表しました。代表作には「夏の葬列」の他に、「青葉しげれる」「男の季節」などがあります。山川は戦後派の作家として、平野謙らと並び称されました。
夏の葬列が書かれた1959年当時の時代背景
夏の葬列が発表された1959年は、高度経済成長期の真っ只中でした。戦後の復興を遂げた日本は、経済的豊かさを享受する一方、戦争の記憶が薄れつつある時代でもありました。そうした中で山川は、戦争がもたらした深い傷跡を描くことで、風化しつつある戦争の記憶を呼び覚まそうとしたのです。
戦争の記憶を描く山川文学の特徴
山川方夫の作品には、戦争体験がもたらした心の傷を克明に描写するという特徴があります。特に「夏の葬列」では、戦時中の一時点だけでなく、戦後になって傷ついた人々がどう生きているかを重層的に描くことで、戦争の影がいかに長く人々の心に残るかを浮き彫りにしています。リアリズムの手法を用いつつ、読む人の感情に訴えかける筆致が山川文学の魅力と言えるでしょう。
夏の葬列のあらすじ ネタバレを含むストーリー解説

物語の舞台と主要登場人物
夏の葬列は、戦時中に疎開先の海辺の町で起きた出来事と、その十数年後の主人公の姿を描いた物語です。主人公は作者の分身のような男性で、東京から疎開してきた少女ヒロ子と親しくしています。二人とも山川方夫がモデルといわれますが、フィクションとして書かれた作品です。
疎開先の昔を思い出す主人公
物語は、大人になった主人公が仕事で疎開先の町を訪れるシーンから始まります。あの時と変わらぬ風景を目にした彼は、一瞬にして当時の記憶がよみがえります。線路沿いの芋畑を歩きながら、あの日の事を思い出すのでした。
芋畑での空襲 少女を突き飛ばした罪悪感
主人公の記憶にあるのは、ヒロ子と芋畑を歩いていた時に襲った空襲でした。米軍機による機銃掃射に、彼は咄嗟に伏せましたが、ヒロ子は彼を助けようと近寄ってきます。しかし彼は恐怖から、ヒロ子を突き飛ばして芋畑に叩きつけてしまったのです。その時ヒロ子は重傷を負い、彼はそれを目撃しました。以来、罪悪感に苛まれる日々が続くのでした。
十数年後に町を再訪する主人公
成人した主人公は、仕事で久々に疎開先の町を訪れます。当時の面影を残す風景の中で、彼は自然とあの日の事を思い出していきます。日常の中で封印していた過去が、生々しく蘇ってくるのでした。
少女の葬列との偶然の遭遇
ふと我に返った時、主人公は目の前の光景に呆然とします。なんと、芋畑の向こうを喪服姿の葬列が通っているではありませんか。あの日の光景とあまりに似ている情景に、彼は息をのむのでした。
少女の生存を知り安堵する主人公
葬列に近づいてみると、棺の上にはヒロ子の写真が飾られていました。しかし彼女は事故の後を生きていたことが分かり、主人公は安堵します。自分は人殺しではなかったのだと。戦後ずっと彼を苦しめた罪の意識から、ようやく解放される瞬間でした。
しかし少女は戦争の傷が元で自殺していた
ところが、葬列の子供たちの話を聞いて主人公は愕然とします。ヒロ子は生きてはいたものの、あの時の事が原因で長く心に傷を負っていたのです。そして数日前、ついに自ら命を絶ったというのです。戦争の爪痕の深さを思い知らされた主人公でした。彼が払拭したかった罪の意識は、ヒロ子の死によって再び彼を捉えるのでした。
夏の葬列の登場人物を解説 主人公と少女の関係性

疎開先で出会った少女ヒロ子
物語のヒロインであるヒロ子は、主人公が学童疎開した先で知り合った少女です。東京から来た二人は意気投合し、よく一緒に遊んでいました。ヒロ子は主人公を頼もしく思っており、いつも彼の側にいました。芋畑で遭遇したのも、そんなある日の事だったのです。
空襲での決定的な場面 突き飛ばした理由
空襲に遭遇した時、ヒロ子は真っ先に主人公の事を案じて駆け寄ってきました。しかし主人公は本能的な恐怖心から、彼女を突き飛ばしてしまいます。白い服を着たヒロ子は格好の的になると、パニックの中で考えたからです。善意で助けに来てくれた彼女を、自分の命が助かる為に傷つけてしまった。それが主人公の抱える罪悪感の核心でした。
大人になり再会した二人の心情の推移
十数年ぶりに町を訪れた主人公は、ヒロ子の葬列と偶然出会います。棺の遺影から、彼女が事故の後も生きていた事を知り、安堵する主人公。しかしその安堵もつかの間、真相を聞いて再び罪に苛まれる事になります。一方のヒロ子は、あの時の恐怖から立ち直れないまま、心に深い傷を残したまま生きてきたのでした。二人は同じ記憶を共有しながら、対照的な心情の推移をたどったのです。
戦争がもたらした深い傷と男の贖罪
ヒロ子の死は、戦争がもたらした傷の深さを物語っています。心の傷は簡単に癒えるものではなく、そのまま人生を蝕み続けるのだと。そしてそれは、傷つけた側の主人公にとっても、一生背負わねばならない十字架となります。彼はヒロ子への贖罪として、彼女と共にあの日の記憶を生き続けねばならないのです。そこには戦争の重みと、人間の再生の物語が重なり合っているのです。
夏の葬列のテーマを考察 戦争の傷跡と人間の再生
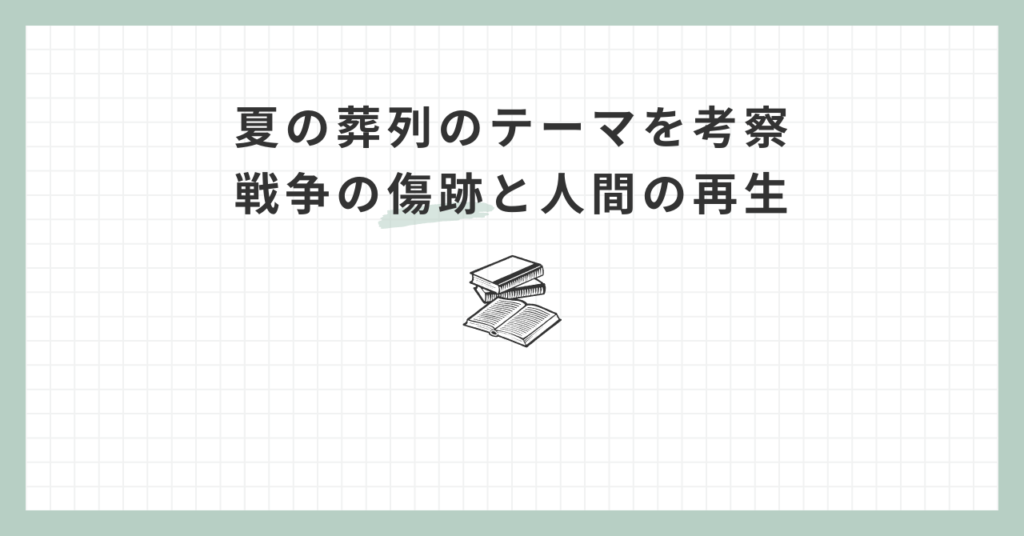
戦争による心の傷の描写 PTSDの先駆的表現
夏の葬列の最大のテーマは、戦争がもたらす心の傷の深さでしょう。ヒロ子が事故から立ち直れずに自殺した描写は、現代で言うところのPTSD(心的外傷後ストレス障害)を思わせます。山川方夫はそれを1959年という早い段階で克明に描き出した先駆者だったのです。主人公の罪悪感も含め、目に見えない戦争の傷を丹念に掘り下げた作品と言えます。
罪の意識を抱える男の心理 自己弁護と自己否定
主人公は事故後、長い間罪の意識に苛まれ続けます。無意識に町を避け、ヒロ子の事を意図的に忘れようともしました。それは罪から逃れる為の自己弁護だったのかもしれません。 一方で自分を責め続ける自己否定の念も捨てきれません。 そのジレンマの中で、主人公はずっと逡巡していたのです。一つの過ちが人の心にいかに深い影を落とし続けるかを、山川は巧みに描いています。
夏が象徴する主人公の時間の停止
物語の舞台はいつも夏です。疎開の夏、再訪した十数年後の夏。夏はあの忌まわしい記憶と結びついた、主人公にとっての特別な季節なのです。彼の中では、戦争も、ヒロ子も、芋畑も、全てが夏で凍り付いたまま。季節の巡りと共に彼も歳を重ねてきたのに、心の中である一点だけは、ずっと夏のままなのでした。それは主人公の心の停滞を象徴しているようでもあります。
人間の再生と救済のテーマ 主人公最後の懺悔
しかし夏の葬列は、単なる絶望の物語ではありません。ラストで主人公は、ヒロ子の死を通して、改めて自らの罪と向き合います。彼はもう逃げない覚悟を決めたのです。そしてそれは、彼の再生への一歩とも言えます。ヒロ子への懺悔の気持ちを胸に、これから生き続ける決意。そこには戦争の傷を乗り越えて生きるヒューマニズムの希望が垣間見えるのです。重いテーマながら、人間の再生を信じる山川文学の真骨頂がここにあります。
まとめ 夏の葬列が伝えるメッセージ

山川方夫が問う戦争責任と戦後の贖罪
夏の葬列は、戦争の傷跡に苦しむ人々の物語です。ヒロ子のPTSDに近い心の傷は、当時は理解されなかった戦争被害者の悲劇を示唆しています。一方主人公の抱える罪の意識は、戦時中の自分の行動を悔やむ戦後日本人の姿とも重なります。山川方夫はこの作品で、戦争の加害と被害、両方の視点から戦争責任を問うています。そしてそれを乗り越える為の贖罪の物語を紡いだのです。
読む人の心に問いを投げかける問題作
夏の葬列は、読者に様々な問いを投げかけてくる作品です。戦争は人の心にどれほどの傷を残すのか。戦争体験を風化させず語り継ぐ意味とは何か。加害と被害の境界線は曖昧ではないのか。そして、私達は過去とどう向き合っていくべきなのか。
夏の葬列が発表された当時、日本社会は戦争の記憶を急速に忘却しつつありました。経済成長に沸く中で、わざわざ心の傷を抉るようなこの作品は、多くの読者に衝撃を与えたことでしょう。しかしだからこそ、この物語の普遍的なメッセージは色褪せることなく、今も読み継がれているのです。
1959年という時代の中で、山川方夫は戦争の問題を真正面から捉えた稀有な作家でした。平和の尊さ、命の重み、人間の再生。そうしたテーマを凝縮した夏の葬列は、単なる戦争文学の枠を超えた、山川文学の真骨頂とも言える作品なのです。



