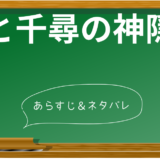本コンテンツはあらすじの泉の基準に基づき制作していますが、本サイト経由で商品購入や会員登録を行った際には送客手数料を受領しています。
『母性』のあらすじと見どころ

母性愛に翻弄される親子三代の物語
教師の清佳(演:永野芽郁)は、女子高生の転落死をきっかけに、母親のルミ子(演:戸田恵梨香)との確執に向き合うことになる。
小説家の湊かなえによる同名小説を映画化した本作は、歪んだ母性愛に翻弄される女性たちの宿命を描いた、重厚なヒューマンドラマだ。
清佳の視点から、母ルミ子、そしてルミ子の母と、3世代に渡る母娘関係が丁寧に描写される。
愛情と呼ぶには歪みすぎた感情を、母から娘へと受け継いでいく様は、胸が痛むとともに、強い共感を呼ぶ。
第13回本屋大賞の候補作となった原作の持つ文学性を、『終の信託』などで知られる廣木隆一監督が繊細なタッチで映像化。
永野芽郁と戸田恵梨香の体当たりの演技にも注目だ。
清佳とルミ子、その母の確執が生む悲劇
幼少期より母ルミ子との関係に悩んできた清佳。
ルミ子もまた、自身の母・清佳の祖母から歪んだ愛情を注がれて育った。
母というものに憧れながらも、どこか拒絶し、それでも母の愛に飢えている。
そんな清佳とルミ子の女心の機微を、原作者らしい鋭い洞察で紡いでいく。
ルミ子が清佳に注ぐ愛情は、時に過干渉とも取れる不気味なもの。
清佳はそれに反発しつつも、どこかで母の愛を求め、すがりついている。
そんな2人の関係が生み出す悲劇が、やがて清佳の身にも降りかかることになる。
母と娘の愛憎に彩られた物語は、ラストに向けて驚愕の展開を迎える。
映画『母性』衝撃の結末ネタバレ

自殺未遂した清佳の真意とは
母ルミ子との確執に苦しんできた清佳は、祖母の死の真相を知り、絶望のあまり自ら命を絶とうとする。
ルミ子の回想シーンでは、清佳の首を絞めている様子が挿入されているが、清佳の認識では自分でロープを首に巻いたことになっている。
ここからは、ルミ子と清佳のそれぞれの「真実」が交錯し、2人の狂気じみた母娘関係が浮き彫りになっていく。
清佳は自らの意思で自殺を図ったつもりでいたが、実は無意識にルミ子の愛情を試すような行動を取っていたのかもしれない。
一方ルミ子にとって、娘の自殺未遂は愛情を示す格好の機会となった。
清佳の首を絞めるシーンは、ルミ子なりの歪んだ愛情表現だったのだ。
ルミ子は清佳に母性愛を示したのか
ルミ子が清佳の自殺未遂に動転し、初めて「清佳」と娘の名を呼ぶシーンは、一見すると母性愛の表れのように見える。
しかし、その裏には「娘を愛せ」という、ルミ子の亡き母から託された呪いのようなものが潜んでいた。
ルミ子にとって清佳は、母の遺言を果たすための「道具」であり、愛するべき対象ではなかったのだ。
清佳が死のうとした瞬間、ルミ子が見せた狼狽は、娘を失う恐怖ではなく、母の呪いを果たせなくなる恐怖だったのかもしれない。
皮肉にも、ルミ子は清佳への愛情を見せることで、母から授かった呪いを次の世代に引き継ごうとしているのだ。
妊娠した清佳の未来を暗示するラストシーン
自殺未遂から生還した清佳は、妊娠していることが明らかになる。
胎内に宿った新たな命は、母から娘へと連綿と受け継がれる「母性の呪縛」の象徴だ。
果たして清佳は、歪んだ母性愛の連鎖を断ち切ることができるのだろうか。
それとも、ルミ子から清佳へ、そして生まれてくる娘へと、呪いはさらに受け継がれていくのか。
ラストシーンに漂う不穏な空気は、「母性」の宿命を暗示しているようだ。
『母性』の衝撃の結末は、観る者の脳裏に強烈な余韻を残す。
『母性』が問うテーマ「母性の呪縛」とは
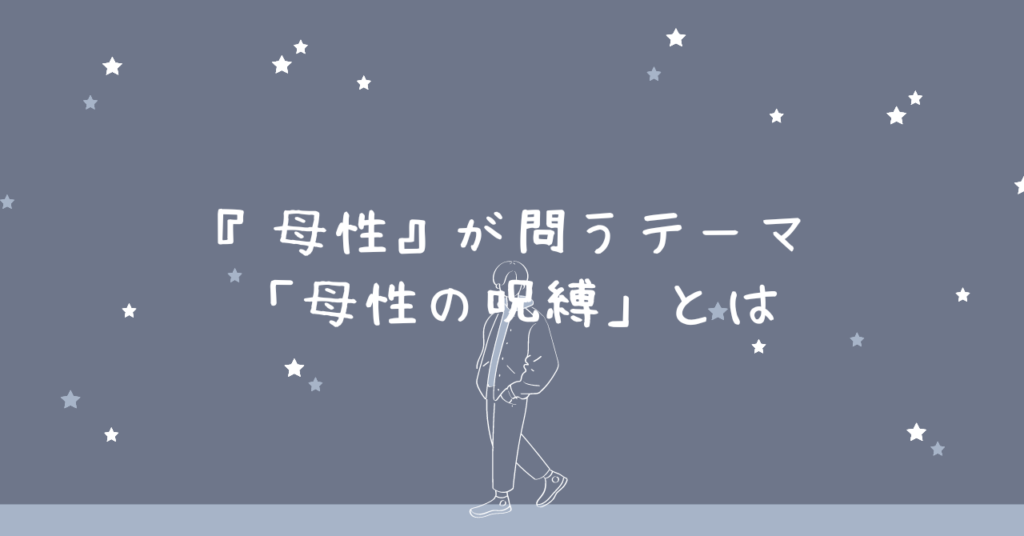
ルミ子の母から受け継がれた歪んだ母性愛
『母性』という映画が投げかける大きなテーマが「母性の呪縛」だ。
ルミ子の母親は、娘に過剰なまでの愛情を注いできた。
自立心を持たせず、母に依存するよう仕向けてきたのだ。
ルミ子 もまた母親と同じように、娘の清佳に執着し、自分の理想通りに育てようとする。
一見美しく見える母性愛も、度が過ぎれば子供の自由を奪い、成長を阻む呪縛となる。
母の呪いは、ルミ子という器を通して、清佳へと受け継がれていったのだ。
清佳はルミ子の呪縛から逃れられるのか
ルミ子の呪縛から逃れられず、自殺未遂に至った清佳。
しかし、命をつなぎ留め、新たな命を宿したことで、彼女の中には変化が生まれつつある。
「母性の呪縛」の連鎖を断ち切るチャンスを、清佳は得たのかもしれない。
一方で、胎内の子が女児であれば、その子もまた「呪い」を受け継ぐ宿命にあるのだろうか。
『母性』は、呪縛から逃れることの難しさを、ラストの清佳の姿を通して問いかける。
世代から子世代へ。そして孫世代へ。
女性たちは、「母性の呪縛」とどう向き合っていくのか。
映画が投げかける問いは、観る者の心に重くのしかかる。
母と娘の物語は、私たち一人一人の物語でもあるのだ。
映画と原作小説『母性』の決定的な違い
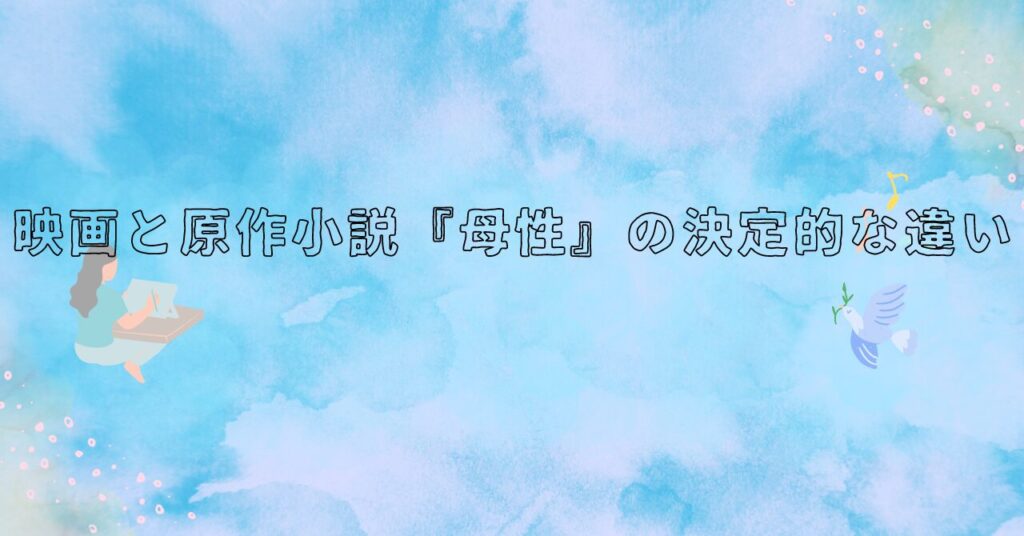
サスペンス色が強調された映画版
映画『母性』は、湊かなえ氏の同名小説が原作だ。
しかし、小説を読んだ人なら、映画版との違いに気づくはずだ。
原作では、清佳の正体は物語の最後まで明かされない。
第三者として登場する彼女が、ルミ子の娘だと判明するのは終盤になってからなのだ。
また、物語序盤で語られる「女子高生転落事件」が、実は清佳たちの物語と重なっていくという叙述トリックも、原作ならではの仕掛けだった。
しかし映画版では、こうしたミステリー色は控えめになっている。
その分ストーリーはシンプルになり、母と娘の確執により焦点が当てられている。
清佳とルミ子の葛藤が先鋭化され、よりサスペンスフルな展開となっているのだ。
ルミ子の第2子を巡る悲劇とラストへの伏線
原作と映画で大きく異なるのが、ルミ子の第2子を巡るエピソードだ。
小説では、ルミ子が30代で妊娠し、生まれてくる子が女児だと確信する。
「母の生まれ変わり」と信じ込み溺愛するルミ子。
しかしある事故をきっかけに流産してしまう。
この悲劇が、ルミ子の心に大きな傷を残し、清佳との関係をさらに悪化させる原因となる。
一方映画には、この第2子のエピソードが登場しない。
その分、清佳の自殺未遂と妊娠ラストの衝撃度が増している。
原作を知る者にとっては、ルミ子の女児への執着が、清佳の妊娠に投影されているようにも感じられるだろう。
ルミ子の「母性の呪縛」は、原作とは異なる形で、しかし確実に清佳に受け継がれていくのだ。
映画版の結末は、原作とは異なる衝撃を観客に与えてくれる。
『母性』登場人物の心理を徹底分析
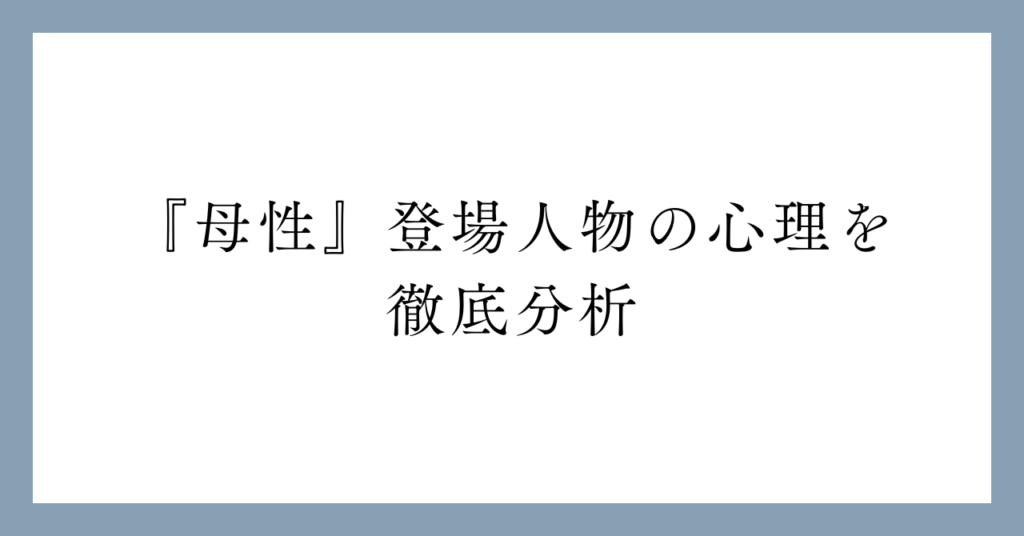
母の愛を渇望するルミ子の悲哀
幼少期、ルミ子は母から過剰なまでの愛情を注がれて育った。
母の愛を全身で浴びることが、ルミ子にとって生きる証だったのだ。
しかしその一方で、ルミ子は母の愛に飽き飽きし、どこかで拒絶もしていた。
自我を確立できないまま大人になったルミ子は、母の承認なしでは生きられない。
母の死は、ルミ子にとって大きな喪失体験となる。
母の愛を失った彼女は、今度は娘の清佳にのめり込む。
清佳に愛情を注ぐことで、亡き母との繋がりを保とうとしたのだ。
しかしルミ子の愛は、時に過干渉となり、コントロールを伴うものだった。
ルミ子自身、愛することと支配することの区別がつかなくなっていたのだ。
母の呪縛から逃れられないルミ子の悲哀が、娘の清佳をも不幸のどん底に突き落としていく。
ルミ子への反抗と屈従の間で揺れる清佳
ルミ子の愛に翻弄される清佳もまた、複雑な心理を抱えている。
幼い頃から母の過干渉に苦しめられてきた清佳は、ルミ子への反発心を強めていた。
自立心や自我を持たせまいとするルミ子に、清佳は反抗する。
学校にも行かず、自堕落な生活を送ることで、母への嫌がらせをしていたのだ。
しかし一方で、清佳はルミ子の愛情を無意識に求めてもいた。
ルミ子に構って欲しくて、わざと心配させるような行動を取ることもあった。
自立と依存が交錯する清佳の態度は、周囲からは理解されづらい。
ルミ子への反抗と屈従を繰り返す清佳。
祖母の死の真相を知り、母への恐怖心が頂点に達した時、清佳は自暴自棄になる。
母の呪縛から逃れるには、自ら命を絶つしかないと考えたのだ。
清佳の心理は、歪んだ母性がもたらす悲劇を如実に物語っている。
『母性』結末から紐解く物語の真相
『母性』の物語を振り返ると、ルミ子の清佳に対する愛情の本質が見えてくる。
ルミ子が清佳に注いだ愛は、母から受け継いだ歪んだ母性愛の表れだったのだ。
それは一種の依存であり、執着でもあった。
娘を思うあまりの行動は、ルミ子なりの愛情表現だったのかもしれない。
しかし、それは子供の自由と人格を尊重したものではない。
ルミ子の愛は、「母性の呪縛」そのものだったのだ。
清佳を縛り付け、自分の理想に沿わせようとするルミ子。
その愛情は、時に清佳に恐怖心を抱かせるものだった。
ルミ子の期待に応えられない自分を責め、母の愛から逃れるために